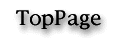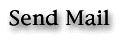神の国は見える形では来ない
水 野 吉 治
新約聖書ルカによる福音書20章27~40節
新約聖書ルカによる福音書17章20、21節
1. レビラト婚
ユダヤ教では、子をもうけないで死んだ長男があれば、次男は、長男の嫁と結婚して子をもうけねばならない、次男が、また子をもうけないで死んだ場合、さらに三男が兄嫁と結婚して子をもうけねばならない、という定めがありました。
これをレビラト婚(レビレート婚・levirate婚・逆縁婚)と言います。
「レビラト」は、ラテン語で「夫の兄弟」を意味する「レビール」から来ています。
この風習は、ユダヤ民族以外にも、パンジャブ、モンゴル族、匈奴(きょうど)(フン族)、チベット民族などにも存在すると言われます。
レビラト婚に対し、ソロラト婚(ソロレート婚・sororate婚・順縁婚・時に「姉妹逆縁婚」とも呼ばれる)は、姉妹を意味する「ソロール」から来ており、妻が死亡した時、夫は妻の姉妹と優先的に結婚することを意味します。
中世キリスト教会では、レビラト婚・ソロラト婚ともに神の意志にそむくものとして禁止されたと言われます。
英国国教会は、ようやく1960年になって両方とも認めたようです。
日本では、明治初年にはソロラト婚(順縁婚)は要許可制となっており、明治8年にはレビラト婚(逆縁婚)は禁止になっていたと言われます。
集団を閉鎖的に守ろうとする方向が強く働くか、異質のものを積極的に取り入れようとする開放的な方向が強く働くかで、レビラト婚・ソロラト婚に対する態度が決まってくるようです。
ちなみに、仏教で「逆縁」とは、
① 仏に反抗し、あるいは仏法をそしることが、かえって仏道に入る因縁となること。
② 自分の修行をさまたげる因縁。
③ 親が子のためとか、仇(かたき)に対してとかいう、逆の関係者のためにする供養。
を意味します。
「逆縁婚」は③の意味から転じて、下位の者が上位の者に対して結婚すると言う意味に使われています。
夫→妻は「順縁」、妻→夫は「逆縁」というふうに使われることもあります。
2. サドカイ派の復活理解
さて、イエス様に敵対するサドカイ派の人々が、イエス様をわなにかけようとして、次のような質問をします。
「モーセのさだめたおきてによれば、
『ある人が子がなくて死んだ場合、その弟は兄嫁と結婚して、兄の跡継ぎをもうけねばならない』
(旧約聖書創世記38章8節・旧約聖書申命記25章5,6節)
となっていますが、かりに7人の兄弟がいて、長男が子がなくて死に、次男も三男も、それぞれ子がなくて次々死に、とうとう7人とも子がないままで死んでしまったとします。
復活の時、嫁は、7人のうちのだれの妻になるのでしょうか。」
サドカイ派は、復活というものはないと主張しているので、復活というものがあるとすれば、レビラト婚で結婚した7組の夫婦(夫7人に妻1人の組み合わせ)のうち、神の国では、どれが永遠の夫婦になるのかという問題が起こるのだ、と指摘して、
「復活を認めれば矛盾が起きる。だから復活はない」
という結論に導こうとします。
イエス様は、サドカイ派の人々に対して、
「この世の子らは、めとったりとつ嫁いだりするが、次の世に入って、死者の中から復活した人々は、めとることも嫁ぐこともない。
この人たちは、もはや死ぬことがない。
天使に等しい者であり、復活にあずかる者として、神の子だからである。
すべての人は、神によって生きているからである」
(新約聖書ルカによる福音書20章34~38節)
と言われます。
サドカイ派の間違いは、めとったりとつ嫁いだりするこの世の関係が、神の国でもそのまま引き継がれると思っているところにあります。
神の国をこの世の図式・枠組みで考えようとするのです。
3. この世の図式
サドカイ派の人々に限らず、およそ人間はこの世の図式を使わずには、何かを考えることも、表現することもできません。
この世の図式は、目に見え、手で触れることができるものだけが実在であるとする前提の上に成り立っています。
テレビで放映されたことは、すべて客観性があり、したがって真理であると、かなり多くの人が思っているのではないでしょうか。
数値や画像で示されたものであれば、疑うことも、検証することもせず、そのまま鵜呑みにしてしまう人がほとんどではないでしょうか。
だれもが、それが科学的な態度であると思い込んでいますが、ほんとうの科学的態度とは、だれもが真理だと思っていることを、まず疑ってかかることから始まるのではないでしょうか。
感覚だけが実在の証しであるとするのは、現代人がとらわれている迷信なのです。
感覚を超えたレベルの話である神の国とか復活とかいうことは、感覚の世界に生きている人間にとっては、理解することも表現することもできません。
復活をあえて理解しようとすれば、この世の図式を使わざるを得ないのです。
4. ファリサイ派の神の国理解
サドカイ派が復活を否定していたのに対し、ファリサイ派は復活を認めていました。
そのファリサイ派の人々が、あるときイエス様に
「神の国はいつ来るのですか」
と質問しました。
サドカイ派と同じくファリサイ派も、神の国をこの世の図式に当てはめて理解しようとします。
イエス様は、ファリサイ派に対して、
「神の国は、見える形では来ない。
『ここにある』『あそこにある』と言えるものでもない。」
(新約聖書ルカによる福音書17章20,21節)
と言われます。
この世の図式から言えば、神の国は見える形で来るはずです。
「人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗って来る」
(新約聖書マタイによる福音書24章29~31節、新約聖書マルコによる福音書13章24~27節、新約聖書ルカによる福音書21章25~27節)
という言葉は、イエス様が、聞く人のレベルに合わせて、神の国の到来を「見える形で」分かりやすく説明しておられるのです。
しかし、ほんとうは
「神の国は、見える形では来ない」
のです。
神の国は空間を超えているからです。
神の国はいつ来るのかというファリサイ派の人々の問いも、この世の時間に当てはめて、神の国の到来を理解しようとしています。
しかし、神の国は、空間も時間も超えています。
だからこそ、「地上の」国なのではなく、「神の」国なのです。
5. からし種一粒
「国」といえば、境界に区切られた面積を持ち、指導者ないし支配者を持つものと考えられますが、ほんとうは、
「神の国は、そのような目に見える形を持っていない」
とイエス様は言われます。
それは、目に見えないほど小さな、無にひとしい「からし種」に似ていると言われるのです
(新約聖書ルカによる福音書13章19節)。
また、無にひとしい「からし種一粒ほどの信仰」が人にあれば、神の国は大きな力を発揮し、
「空の鳥が来て枝に巣を作る」
(新約聖書マタイによる福音書13章32節)
ほどになると言われます。
「からし種一粒ほどの信仰」があれば、山を動かすこともできるのです
(新約聖書マタイによる福音書17章20節)。
「無にひとしい神の国」は、「無にひとしい信仰」に対応しています。
信仰は、神の国を映すものだからです。
神の国は、上より垂直にこの世に来て、地上と交わります。
それは位置だけあって、面積のない「無の一点」です。
「無の一点」は時間を超えていますから、過去も未来もありません。
常に現在です。
「現在」という幅も長さすらありません。
「無の一点」は空間を超えていますから、地上のあらゆるところに同時に存在します。
常に現在であり、常に遍在です。
「無の一点」を認識する人間は、その認識を誇ることはしません。
自らもまた「無の一点」になるのです。
人間が「無の一点」になるとは、エゴを無くすことです。
「わたしの願いどおりではなく、み心のままに」
(新約聖書マタイによる福音書26章39節)
という姿勢をとることです。
その姿勢は、この世の粗雑な認識によっては、とらえられません。
しかし、その姿勢から出てきた結果は、認識できます。
それが「十字架」です。
6. 十字架と復活
無になり切った十字架から展開するのが復活です。
十字架が単なる無ではなく、「神による無」であるように、復活もまた単なる生ではなく、「神による生」です。
「神によらない無」は観念的な無であり、「神によらない生」は、いつかはまた死なねばならない生です。
復活の生は、十字架という断絶を経た生です。
十字架という断絶は、親子、兄弟、夫婦のきずなを断ち切ります。
断ち切られたきずなは、復活によって回復するのでしょうか。
回復しますが、以前のままのきずなではありません。
古い生がそのまま繰り返されるのではありません。
繰り返されるなら、それがいわゆる「輪廻転生」であり、「霊魂不滅」です。
「輪廻転生」は、古い生が古いままで、同じところをグルグル回っている状態です。
「霊魂不滅」も、断絶を否定した直接性の世界です。
どちらも「神なき永遠」であり、「さまよえるオランダ人」のように、死ぬことを許されず、永遠にこの地上をさまよっていなければならない「のろわれた無限」です。
その「無限」は、二枚の合わせ鏡のように、自分が無数に映っているようなものです。
古い生が無限に映っているだけのさびしい、救いのない世界です。
人間を地上に縛り付けている古いきずなが断ち切られ、新しい生が開かれるのが復活です。
7. 霊の体・復活の体
結婚は、有限なこの世の関係です。
その関係が、神の国にまで持ち込まれることはありません。
たしかに、肉体をもって生きているかぎり、夫婦という関係は存在し、愛も存在します。
相手が死んでも、また神の国で再会できるだろうという確信があります。
それが愛です。
しかし、その愛は、死をへ経た愛ですから、有限なこの世の愛ではありません。
この世を超えた永遠の愛です。
また、特定の相手は、神の国の中では、この世の存在とは違った姿で存在するのです。
「存在」とは言うものの、「ここにいる」とか「あそこにいる」と言えるような形では存在しません。
神の国が「ここにある」とか「あそこにある」と言えるような形で存在しないのと同じです。
たしかにあるのですが、位置だけあって、面積のない、無の一点としてのあり方をしています。
聖書で、
「霊の体」・「復活の体」
(新約聖書コリントの信徒への手紙一・15章35~49節)
として述べられているあり方です。
そのあり方、つまり霊の体・復活の体や神の国のことは、有限なこの世の言葉では、理解することも、説明することもできません。
あえて理解し、説明しようとするならば、この世の図式を使った「神話という形」を取らざるを得ません。
だからといって、霊の体・復活の体や神の国が「神話」であるわけがありません。
それはあくまでも「実在」なのです。
しかし、その実在は、「神話という形」を取らなければ、理解も説明もできないのです。
神の国の現実を、「神話という形」で理解し説明しようとすれば、矛盾や問題が起こるのは当然です。
だからと言って、霊の体・復活の体や神の国が存在しないということにはなりません。
存在しないのは、移ろい行き、すぐ消え去る「肉の体」であり、「古いいのち」であり、「この世の国」なのです。
「肉の体」や、「古いいのち」や、「この世の国」は、いわば、影のような存在です。
過ぎ行くものであり、実体のない、はかない存在です。
8. 神の国での再会
死んだ、愛する人が存在しないのではなく、愛する人が、「肉の体」を持ち、「古いいのち」に生き、「この世の国」の関係をそのまま保っていると考えるのが間違っているのです。
したがって、私たちが死んだあと、神の国で、愛するものとふたたび会うことができるということは、事実であっても、この世の関係そのままで、生前の記憶を保持したままで、肉の体において、ふたたび会うのではありません。
私も相手も、復活のいのち・復活の体として、新しくされて、会うのです。
まったく新しい出会いであり、新しいいのちに生かされている者同士の出会いなのです。
それを、イエス様は、「天使のようになる」とおっしゃっています。
地上で、愛する人の写真を飾り、それを見て、愛する人を想うということは、意味のある行為です。
しかし、その愛は、もはや肉の愛ではありません。
肉は死んだのです。
かつての肉の愛は、古いいのちのままの、いつかは朽ちてゆく愛でした。
今や、私も相手も、霊のいのちに生かされています。
肉の愛からすれば、愛する相手以外は、すべて他人でした。
しかし、今や、他人は一人もありません。
見渡すかぎり、霊のいのちに生かされている、親しいものばかりです。
特定の相手だけを愛する愛は、もはや死んでしまったのです。
生きているのは復活のいのちだけです。
「すべての人は、神によって生きている」
とイエス様が言われるように、神によって生きているもの同士の間には、特定の相手に対する愛はありません。
特定の相手との再会は、
「特定の相手に限られた再会」
ですが、すべての人との再会は、
「特定の相手を超えた、喜ばしい、永遠の再会」
です。
憎しみも愛も超えた、復活のいのちに生かされている者同士の再会です。
もはや、2枚の合わせ鏡によってでもなく、おぼろに映る鏡によるのでもありません。
「顔と顔とを合わせて」一つにされたいのちの再会なのです。